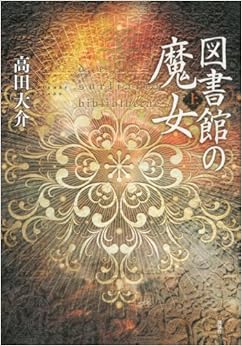高田大介氏の図書館の魔女(下)を読んだ。上巻では後半に刺客に襲われ物語が大きく動き出すかと思いきや、下巻の進行も緩やかに動き出していく感じだった。
まず、マツリカは魔術書・錬金術書を類をこき下ろし、禁書にするなど馬鹿馬鹿しいと一蹴するの所から始まるのだ。その後ストーリーでは、ニザマの宦官の策謀が見えてきて、それに対抗する手はずも着々と整える図書館であったが、そこに第二の刺客が遣わされ、マツリカの利き腕の左手の動きが封じられてしまった。しかし、キリヒトとの間にはあの指話による会話は健在であった。マツリカはニザマの宦官の野望を言葉の力で打ち砕くべく、戦いを挑んでくのだった。本書の250ページ辺りから、物語はスピードを速めて一気呵成に進行していく。
今回、図書館の魔女上・下を読みつつ、この本は一体どんなジャンルに属するのだろうと、づうと考えていた。ファンタジーとはちょっと違うと思う。なぜなら、超自然的なことも幻想的なこともほとんど出てこず、唯一ニザマの刺客を求めて、古アルデッシュに踏み込んだマツリカ一行を襲ったゾンビ兵ぐらいだろう。なにせ、メインヒロイン自身がが魔術を全く信じていないのだから、そういうストーリは出しにくいだろう。思うに、これはある種のミステリーではないかと思った。それも言語に対するミステリー。これは著者が言語学の研究をしていることとも符合する。
上巻において「こんな嵐がひどくなると知りたらましかば」というちょっとしたフレーズから、その裏に潜んでいるもろもろを導き出すところは、あの「9マイルは遠すぎる」思い出すような展開だし、下巻においては、ニザマ帝の宮殿にあった書と帝室典医の言葉使いから、その書の真の書き手を推理する辺りは、まさにミステリーだと感じた。ただ、その目論見がうまくいったかどうかは疑問が残る。というのも、読者は本書で述べられている文法的な文化的な背景が事前にわからないので、それが正しいのかどうか判断できないからだ。なので、せっかく書かれているところがストーリーとして生きていないと思われる。もっとも、だからと言って本書の面白さがなくなってしまうわけではない。
本書において、ニザマの宦官の策謀は図書館の働きにより潰えたのだが、まだ物語は終わっておらず、下巻の最後の部分は次のストリーへのプロローグという感じになっている。実際、同作者による「図書館の魔女(烏の伝言)」も刊行されており、本作の続きであろうと推測したのだが、以下のあらすじからすると、直接つながっていないような気もする。いずれにしても、読まなくてはわからない。
霧深いなか、道案内の剛力たちに守られながら、ニザマの地方官僚の姫君ユシャッバとその近衛兵の一行が尾根を渡っていた。陰謀渦巻く当地で追われた一行は、山を下った先にある港町を目指していた。
剛力集団の中には、鳥飼のエゴンがいた。顔に大きな傷を持つエゴンは言葉をうまく使えないが、鳥たちとは、障害なく意思疎通がとれているようだ。そんな彼の様子を興味深く見ていたのは、他ならぬユシャッバだったーー。