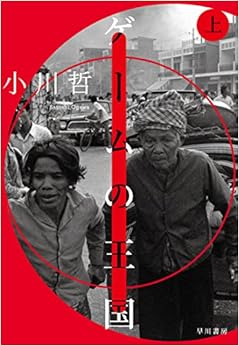小川哲氏のゲームの王国を読んだ。
このSF小説は一体どう理解すればいいのだろう? 本書は上巻・下巻に分かれており、上巻は約400ページ、下巻は約360ページの紛れもない大長編なのだが、上巻を読む限りは、これをSF小説と呼んでいいのだろうかと、疑問が湧いてきてしまった。このことは、事前の知識として知ってはいたのだが、ここまで徹底的になっているとは思わなかった。
上巻
上巻の舞台は1950年代後半~1970年代後半のカンボジアになっている。一人の主人公はロベーブレソン村の村長サムの息子ムイタック。ムイタックはあだ名で、本当の名前はソック、彼は極度の潔癖症で、執拗に体を清めないと気が済まない。しかし頭脳が明晰だ。もう一人の主人公はソリアという名の孤児の少女。サロト・サル(後のポル・ポト)の子供だという噂もあるが、真偽不明。育ての両親をカンボジアの秘密警察にいわれのない密告のせいで殺された。彼女は真実を見抜く能力がある。
このムイタックとソリアが様々な偶然が重なり、クメール・ルージュによるプノンペン陥落の日に出会うことになる。そこで二人はチャンドゥクというトランプゲームをする。ムイタックはゲームをするときに手を抜いて、わざと負けていた。そうしないと、他の子供たちがやる気をなくすからだ。しかし、ソリアとのゲームでは、本気でプレイしても、完全には勝てなかった。そんな相手は、ソリアが初めてだった。二人は再びゲームをすることを約束するが、革命のためその約束は果たされることはなかった。
そして、ポル・ポトは国の実権を握っていき、カンボジアは全く救いのない国になった。密告・拷問・処刑。食料不足・強制労働。ありとあらゆる望みが国から失せて行った。そんな悲惨な時代を二人は生き残った。ソリアの目的ははクメール・ルージュを、ポル・ポトを倒すことになった。ムイタックは村を守るために奮闘した。そんな二人が再び交わるときに、ロベーブレソンの村は悲劇に襲わる。ムイタックはその悲劇はソリアのせいだと直感し、必ずソリアを倒すことを心に誓うのだった。
下巻
物語は一気に半世紀の時間を超える。主な時間軸は2023年に設定されている。ポル・ポト政権崩壊後、暗黒の時代は終わった。しかし、依然として不正がはびこるカンボジアを何とか正しいルールが律する国にしようと、ソリアは自分がルールを作る側である政治家を目指し、着実に歩んでいた。ソリアは目的のためには手段を選んでいる余裕がなかった。一方ムイタックは大学教授になっており、脳神経科学の研究をしていた。ロベーブレソン出身のアランという少年とソリアの養子になったリアスメイがムイタックと巡り合い、チャンドゥクという脳波を用いて制御するゲームを作成していくことになる。そして、そのゲームで再びムイタックとソリアは戦うことになる。
下巻は残りページ数と話の進み具合から、いったいどういう結末になるのだろうと思いながら読み進めていた。うーむ、最後の終り方はどうなのだろう。いろいろ面白い設定が出てきていて、例えばP120という脳波とか、部族内でルールを厳格に守りあたかもゲームをしているように生活するモーリタニアのソンクローニ族のエピソードとか、ゲームから偽記憶が形成されるとか、あるいはさまざまな異能を持つ登場人物(輪ゴムが切れることで人が死ぬことを知るクワン、土と会話するプク、不正に対して性的な興奮を覚えるカンなど)ストーリ自体は面白く読み進めていたのだが。
特に一番興味深い展開だったのだが、下巻のP256の
「ルール違反をするなと命令するのではなく、そもそも違反ができない状態にするわけだ」
への回答が明かされるなくストーリーが終わってしまった。これが「教室からごみを無くすために、教室自体を、学校をカンボジアからなくす」というアナロジーで想像すると、ルールを無くしてしまうということになるのだが、そいうことではないと思う。目指しているのはゲームの王国なのだから。ゲームの王国と呼ばれたソンクローニ族の話から考えると、「掟を守るために最善を尽くす。それが守られないときは追放される」だ。だが、これをルールとした国家は可能なのだろうか?
それと、上巻でのソリアとムイタックのゲームはソリアが勝ったのだが、ソリアは自分がムイタックに負けたと記憶している。これが何かの伏線になっているのかと思ったのだが、その部分に触れることなく物語が終わってしまった。特に深い意味はなかったのだろうか?