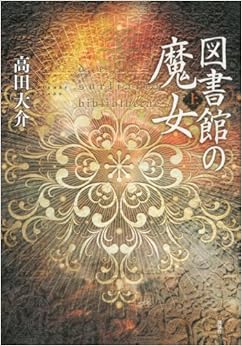高田大介氏の図書館の魔女(上)を読んだ。本書はとにかく厚い。ページ数で652ページあり、厚さからすると、2冊分ぐらいに相当するのではないだろうか。上巻には第一部と第二部が収録されている。しかし、この上巻では、ようやく物語が動き出したところで、今後どのように物語が進んでいくか全くわからない状況だ。しかも、下巻は上巻よりも厚く805ページもある。
架空の世界での物語で、時代区分は封建制時代を想像させる。物語は鍛冶の里で暮らしていた少年キリヒトと師匠が一の谷(この世界で都市がある所)からやって来た図書館付のロワンと一の谷に向かうところから始まる。キリヒトの目的は一の谷にある図書館にいる魔女マツリカに仕えることだった。マツリカは耳は聞こえるが、言葉を発することができず、そのため彼女は手話と操って、他人と会話をする。キリヒトはマツリカの手話通訳士になることを期待されていた。マツリカはまだ10代半ばの少女であり、魔女と言ってもそれは比喩的な意味だ(性格は意地悪で、言葉は辛辣であり、誰にも容赦がない)。「古今の書物を繙き、数多の言語を操って策を巡らせるがゆえ」に魔女と呼ばれている。そのほかに司書のハルカゼとキリンの二人のマツリカより年上の女性と合わせて、図書館の三魔女と揶揄されている。
一の谷の図書館は高い塔になっていて、そこに所蔵される資料を世界中の学究・賢人が求めてやってくるという。上巻においては、資料を求めてやってきたものはまだいない。
ページ数が多いことから想像できるように、物語は詳細が語られて、ストーリの展開は緩やかである。140ページ辺りで二津間(ニザマ)国の宦官ミツクビが何らかの策を一の谷に対して企んでいることが示唆されるが、その話はあまり進展しない。所々に一の谷およびその周辺国の状況が挿入されるが、図書館に差し迫った危機は訪れない。
物語では、マツリカが新しい指話(四本の指の伸ばす動き、縮める動き、遊ばせる動きを組み合わせて、それを音に割り当てる)を発明して、キリヒトに試したり(この指話のおかげで、暗いところでも二人は意思疎通できるようになる)、図書館の塔の傍にある植物園の下に忘れられて地下水道があり、それが城外の町にまで続いていてることをマツリカとキリヒトが発見し、それを探検したりする。この探検も後々ストーリにかかわってくることになるので、無駄に挿入されているわけではない。
520ページ辺りでようやく、マツリカ・キリヒトが川遊びをしているときに、3メータ近くの巨人蛮族の刺客に襲われる、ここから一気に物語が動き出すのかどうか、まだ下巻を読み始めたばかりなのでわからない。