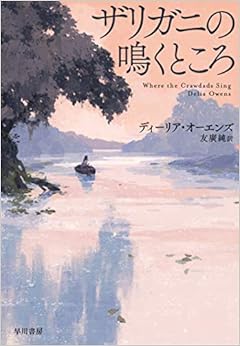ディーリア・オーエンズのザリガニの鳴くところ (原題 Where the Crawdads Sing)を読んだ。
この作品は北上ラジオの第13回目で紹介されていた。
ディーリア・オーエンズ『ザリガニの鳴くところ』は、2020年を代表する素晴らしい小説だ!「北上ラジオ」第13回 Presented by 本の雑誌社 - YouTube
舞台はノースカロライナ州のバークリー・コーヴという村。その辺りの海岸の土地は湿地地帯で、沼も多かった。そのような土地はまともな人間は引き付けづ、そこに住み着く人間はそれなりの理由があった。プロローグでは1969年にその町の火の見櫓でチェイス・アンドリューの死体が発見されたことが提示されるが、その時点で読者にはチェイス・アンドリューは何者なのかということは一切明かされない。
この物語の主人公はカイアと呼ばれていた少女だ。彼女の物語は6歳の時、1952年から始まる。彼女の一家はその湿地の小屋に住んでいた。ある日カイアは母が家出したところから彼女の物語は始まる。その後、年の離れた兄と姉二人もいなくなった。そして、年が一番近かった兄のジョディも「このうちにはいられない」と言って、どこかへ去っていった。なぜ、彼らが去って言ったのか?それは父親のせいだ。父親のジェイクは第二次世界大戦でドイツ軍と戦い、爆弾で左足の太腿をやられ、一生治らない怪我をした。一家の収入源は父親の障害者手当だけだった。父親は酒に溺れ、家族を殴った。それからプイといなくなり、2~3日帰ってこない。典型的な暴力と責任の放棄だ。そんなことが繰り返され、母親がいなくなったことが引き金になり、一家は崩壊したのだった。カイアはなんとか父親と折り合いをつけながら、生活を続けたが、カイアが10歳になったころ、母親から手紙が来た。学校に通っていないカイアは文字が読めなかったので、目立つところにその手紙を置いておくと、手紙を読んだ父親は怒り狂い、父親もいなくなった。そして、カイア一人がその湿地に残された。そんなカイアの窮状を救ってくれたのが、町はずれで雑貨商を営む黒人の通称ジャンピンと妻のメイベルであり、学校に通っていないカイアに文字などを教えてくれたのは兄のジョディの友達だったテイトだった。彼女は全くの孤立無援だったわけではないが、ほとんどの村の住人は「湿地の少女」と呼んで、排除し、蔑んでいた。
この小説はカイアの物語が1952年から語られて行き、その間に1969年に起きたチェイス・アンドリューの件の調査が挟み込まれながら進んでいく。チェイス・アンドリューはウェスタン・オートを営むアンドリュー家の一人息子で、高校ではクォーターバックのスター選手だったので、村でも一目置かれる存在となっていた。そして、このハンサムな若者は村一番の美人と結婚したのだった。当然この1952年の物語と1969年の物語はやがて交わることになる。つまり、カイアとチェイスの行動線が交わるのだ。実は、チェイスはかなりの女たらしで、手当たり次第に女に手を出しているということがやがて明らかになってくる。
物語の後半は法廷の場面となっていて、表紙の見返しのところにもあるようにカイアに疑いの目が向けられているのだが、この事件は物的証拠が極端に少なく、物的証拠から事故なのか、殺人なのかもわからない状況なのだ。そういう意味ではこれも心理の小説だ。
この物語の父親のジェイクも死んだチェイスのある種のくずだ。最初父親は足のケガがもとで、駄目になったのだと思ったが、そうではないことが物語で明かされるし、村でも一目置かれる存在のはずのチェイスも上に書いたように裏の顔があるのも明らかになる。一方カイアは孤独に耐えながら孤高に生きたてきた。彼女は湿地の生物の標本集めたりやスケッチをため込んでいた。それは単に生物・自然への興味だ。テイトに文字を教わり、独学で科学や生物について調べていたことがそれに繋がっていったのだ。しかし、彼女はやはり孤独だった。北上氏はラジオの中で「孤高ではあるが、孤独ではない」と言っているが、私は彼女は孤独だったと思う。そうでなければ、カイアとチェイスの物語が交わることはなかったと思うからだ。
この著者は生物行動学者だそうで、彼女の描く自然の描写や物語の中に散りばめられる生物に関する知識も読んでいた面白いところだった。
雌キツネは飢えたり過度のストレスがかかったりすると、子どもを捨てることがある。子どもたちは死んでも、雌キツネは生き延びられる。そうすれば、状況が改善したときにはまた子どもを産んで育てられる。
これはカイアが母親に捨てられたことを納得するために持ち出したことだ(最初はジュディが「母さんは飢えていないから戻ってくる」とカイアを慰めたのだが)。だから、捨てられたのは理解できる。でも、戻ってこなかったのは許せなと嘆くのは印象的だった。
この本のタイトルになっている「ザリガニの鳴くところ(Where the Crawdads Sing)」は本書の中でテイトが「茂みの奥深く、生き物たちが自然のままの姿で生きている場所ってことさ」と言っているが、もともとは著者の母親が子供の頃に彼女に言った言葉がもとになっているようだ。
hello-sunshine.com
ザリガニというとcrawfishとかcrayfishという単語が思い浮かぶが、crawdadというのは今回初めて知った。
英語版のwikipediaを見ると、映画化が進行しているようだ。この物語は長いので、このままでは映画にはできないと思うのだが、どのようなストーリーになるのだろうか?楽しみでもあるが、ちょっと不安な感じもする。
本書を読んでいて気になった点がある。それはカイアがポーチで寝起きしているように書かれているのだが、ポーチというのは家の外で庇がある玄関につながる部分だと思うのだが、そうすると彼女は家の外で寝起きしていたということなのだろうか?