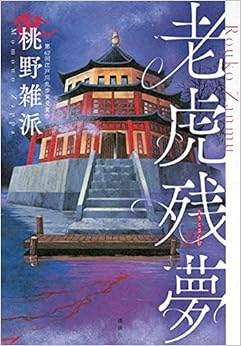桃野雑派氏の老虎残夢を読んだ。本作は第67回江戸川乱歩賞受賞作で、読もうと思っていたのだが、何となく後回しになっていた。
この小説は12世紀ごろの中国が舞台になっている。武侠小説 x 百合 x 特殊設定ミステリーという組み合わせの小説で、この作品を読むまで「武侠小説」というジャンルがあること自体知らなかった。武は武術のことで、侠は義侠心のことだろうか。小説の中の武なので、なんだかとてつもない力があるようで、内功・外功とかなじみのない言葉が出てくるので、最初はちょっと読みにくく感じた。
弓のような形の湖の中心に八仙楼は建っていた。弦の長さは約600メートル、弦から弧の一番遠い所までの距離は300メートルで、通常は楼には船で渡るの。だが、武術の達人梁泰隆やその弟子の蒼紫苑は内功の力で水面を蹴って飛ぶようにわたっていく。ちょっとやそっとの修練ではその域には達しない力だ。泰隆は外から客人三人を招き、そのうちの誰かに奥義を伝授するという。紫苑は自分には奥義が伝えられないことに失望を感じるが師に逆らうことはできない。外からやって来た客人は泰隆と同門の蔡文和と楽祥纏、それと僧侶の為問だった。泰隆は翌日には誰に奥義を伝えるか言うと言っていた。だが、翌朝養女の恋華が朝食を八仙楼に運ぼうとするも、船が楼側にあり渡れなかった。紫苑が昨夜最後に見た時には船はこちらの岸にあったはずだ。文和が竿と釣り針で船を引き寄せ、紫苑、文和、祥纏、為問が八仙楼に辿り着くと泰隆は口から血を流して死んでいた。
舟がないと八仙楼には渡れないので、一種の密室状態になっているというのがこのミステリーの重要なポイントであるが、なんせ「武侠」なので読者の知らない方法で行き来できるかもしれない。実際文和は竿と釣り針で船を引き寄せているのだから。そこが読んでいて何とも判断がつかないところで、特殊設定というこの小説の弱い所なのではないかと感じた。舞台背景は面白く感じたのだが、この特殊設定になじめなかった(どのように超人的力をとらえていいのかよくわからなかった)。後半推理が他殺なのか自殺なのかの間で行ったり来たりしたのも、意外性に繋がらなくて、面白さがあまり感じられなかった。