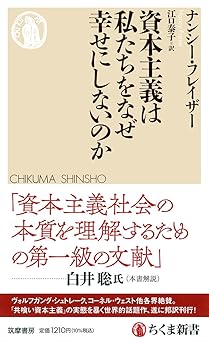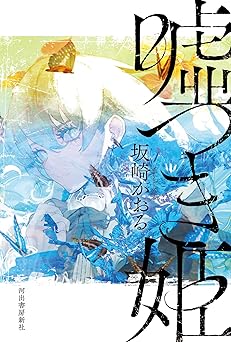ナンシー・フレイザーの資本主義は私たちをなぜ幸せにしないのか (原題 CANNIBAL CAPITALISM)を読んだ。
著者は資本主義を共食い資本主義と名づけている。資本主義そのものがそれは他者を食い物にしてしか成り立たたないからだ。食い物にすると言うのは具体的には収奪と搾取だ。収奪というとかつての植民地諸国からの収奪をイメージするが、それだけではなく、資本主義はエネルギーや原材料を自然環境に依存しており、その調達に関しては正に収奪で、奪い取るが、その後のことは一切考えていない。その結果の一つが、我々が直面している気候変動だろう。搾取に関しては、著者は「食料や衣服など低価格の生活必需品を供給し、より低い賃金で生活できるようにする」と書いている。これを読んでハッとした。実はこれはバブル崩壊後の日本経済園もだからだ。あの長いデフレ期間を搾取という視点で考えたことはなかった。
資本主義に対する解決策が社会主義だと著者は説くのだが、かってのソビエトや中国のイメージがどうしても抜けきらないので、私はそこにも違和感を感じる。「社会による資本の統制」とか「資本に対する社会の優越」というような社会主義というのがうまくイメージができないのだ。ある日を境に全く違った社会に移行するというのは混乱が非常に大きいので、徐々に移行するしかないのだろう。そのためにはどのようにシステムを移行するかの議論も必要だと思う。