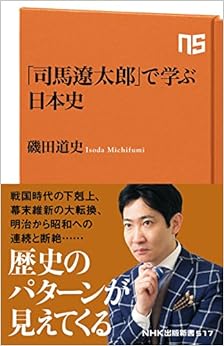冲方丁氏の十二人の死にたい子どもたちを読んだ。ある目的をもって廃棄された病院に集った六人の少年と六人の少女。合わせて十二人。なぜ、彼らの人数を十二人にしたのかは、「怒れる十二人の男たち」に合わせて作者は十二人にしたのだろう。登場人物からは、なぜ十二人という人数になったのかは語られない。彼ら十二人の目的は、この病院で同時に自殺することだった。心中ではなく、殺人でもなく、自殺すること。しかし、何かの手違いがあり、そこもう一人の少年が紛れ込んでいた。しかも既に死んでいるようなのだ。そして、誰も彼のことを知らないという。このまま自殺を決行すれば、彼を殺した受け取れかねない状況になってしまっていた。
ここから物語が動き出す。主催者の少年は、このまま集団自殺を決行すべきかどうかで、多数決を取り、決定しようと提案する。そして、純粋にこの状況に疑問を持ち、このままでは集団自殺できないと、反対するものがいて、彼らは議論を開始していくのだ。怒れる十二人の男たちの様に。
作者は登場人物に謎解きにたけた少年を配することで、本作をミステリーに仕立てているが、物語の中で彼らがなぜ死を望むのかを語らせ、最後にはその死を望んでいる状況も解決するように話を進めていく。その部分は若干引っ掛かるものもあるが、うまくまとめていると思った。
この小説を読んで、久々に十二人の優しい日本人を見た。この映画もよくできていると思う。そして、本家本元の怒れる十二人の男たちも見たくなった。