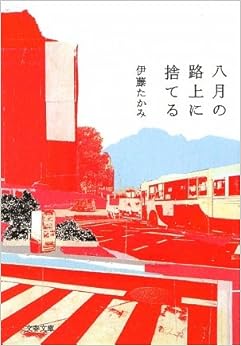伊藤たかみ氏の八月の路上に捨てるを読んだ。以前SmartNewsの読書のタブに以下の記事が配信されていて、それを見て興味を持ったので読んでみた。2006年の芥川賞受賞作ということである。
ここに書かれていることは、ある意味衝撃的だった。
話をおもしろくするために、次々と偶然をつみかさねていくような作り話ではなく、一人の人間がそこに生きていて、苦しんだり悩んだりする姿を、ありのままに描く、というのが本物の「小説」だということになるでしょうか。
逍遙はそれを、「人情と風俗」と表現しました。これはちょっとふるい言葉なので、ここでは「人間と社会」を描く、というふうに言っておきます。
この部分は、まぁ理解できなくもない。
殺人事件が起こらない。主人公が変身しない。わくわくするような展開がない。最後に謎が解き明かされるということもないし、そもそも謎みたいなものが出てこない。それでは何を楽しみにして次のページに進めばいいのか、わからなくなります。
でも、それが文学なのですね。
本を読んでいたり、ラジオでドラマや朗読を聞いていると、何の結論もなく終わってしまう物語に出くわすことがあった。そして、何か消化不良なようなものを感じることがあったが、それはそのものが「文学だったから」ということか。
本を読んでわくわくしたい人は、「まんが」や「ファンタジー」を楽しんでください。でもそれでは、永遠に現実から目をそらして、空想の中にひたっているだけではないでしょうか。
近代(現代)の人間は、社会というものに目を向け、その中に自分を位置づけて、いかに生きるべきかを真剣に考える。そうやってたえず社会と自分との関係というものを考えていないと、めまぐるしい社会の動きに対応できなくなってしまう。それが現代社会なのです。
「いかに生きるべきかを真剣に考える」べきなのかもしれないが、これは疲れるなぁ。本を読むときぐらい、リラックスしたい。
小説を読んで涙が流れてきた時、泣いている自分に感動することがありますし、主人公といっしょになって苦しみながら、ふと本のページを閉じて、自分は安全地帯にいると思って、ほっと息をつく……。
自分は、今までこんな経験をしたことはない。泣いている自分に感動することなどないし、「泣いている自分に感動する」理由が、「自分は本を閉じるだけで、安全地帯に戻れるから」なんて。慥かに、それぐらい自分の心に余裕があり、書かれている内容を第三者的に突き放す心情的な冷徹さがなければ、「いかに生きるべきか」などを考えることはできないかもしれない。
さて、本書「八月の路上に捨てる」だが、自販機に飲み物を補充する会社でトラックのドライバーをする水城さん(女性)と男性アルバイトの敦が、水城さんがドライバーを辞めて総務に転属になる最後の日に、補充作業の間に敦が自分の離婚を語る話だ。自販機に飲み物を補充する作業を淡々と描写する部分に、シナリオライターを目指していた敦と編集者になりたかった離婚する妻と、敦の不倫相手のストーリーが挟み込まれているだけだった。
面白いと思ったのは「煙詰め」のエピソード(P28、P66)。これが、最後の所で、
みんな風景に溶けてしまった。煙みたいに、どこかへいった。明日になれば千恵子も消える。戸籍謄本の山の中に消えてしまう。馬鹿な敦だけがここに残されるのだった。
につながって、いい雰囲気になっていると思った。