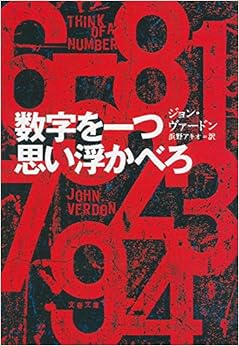フランシス・ハーディングのカッコーの歌(原題 Cuckoo Song)を読んだ。嘘の木 - 隠居日録が面白かったので、こちらの作品も読んでみたのだが、巻末の解説によると、カッコーの歌の方が本国では先に出版されていたということだ。
主人公は十一歳の少女トリス(本名 テレサ)。何か非常に混乱した状況から物語始まる。最初は自分が誰で、周りにいる人たちも誰だかはっきりわからないぐらい混乱していた。どうやら両親と妹と別荘に来ていて、近くの池に落ちたところを助けられたようなのだ。だが、妹のペン (本名 ペネロペ)はトリスの事を偽物だと非難する。妹は癇癪持ちの様で、質問してもまともに答えてくれそうにない。それからいろいろ奇妙なことがトリスの周りでおこる。いくら食べても空腹が収まらない。日記のページが破り取られていたり。ベットには毎晩小枝や枯葉が落ちていたり。父と母は何かを隠しているようだが、それがなんだかわからない。どうやらその両親の秘密は第一次世界大戦に行ったきり戻ってこない兄のセバスチャンに関係しているようなのだが…。
この小説のアメリカ版の表紙はちょっとドキッとするような感じになっていて、ホラー小説ではないかという印象を与える。
https://www.amazon.com/Cuckoo-Song-Frances-Hardinge/dp/1419719394/:www.amazon.com
それと比べると日本版の表紙は穏当で、本作は純粋なファンタジー小説になっている。全体のページ数が430ページぐらいあり、前半の4分の1が過ぎるまでは、トリスの周りで起きる不思議なことが主で、どうなるのだろうという感じはするのだが、物語が動き出している印象が少ないので、もう少しテンポよく進むか、物語の構造を早く知りたいと思いながら読ん。だた、その部分を過ぎると、なぜ妹のペンがトリスが偽物だと言ったのかが判り、物語にもスピード感が出てきて、さらに今までの物語の色々なピースがまとまり始め、そこからは物語に引き込まれていく。物語は「後七日」、「後六日」と何か期限が切られていて、時間との勝負ということが示唆されていて、トリスはその期限までに問題を解決しなければならないのだ。
この小説は単にファンタジーというだけでなく、「嘘の木」のように家族の物語でもある。ただこの本のタイトルに郭公が含まれているのは托卵の暗喩だとすると、トリスは家族の中の異物を意味しているのだろうが、それも含めてやはり家族の物語なのだろう。