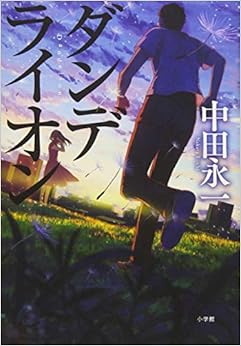中田永一氏のダンデライオンを読んだ。ミステリーの分類になっているようだが、どちらかというとSFだと思う。もちろん、ミステリー要素もあるのだが、それは主ではなく従ではないかというのが読後の感想だ。
物語は1999年と2019年が一人の男の中で交差することで進んでいく。その男は下野(かばた)蓮司。下野と書いてかばたと読ませるのを初めて知った。下野蓮司は2019年の10月公園の何者かに殴られて気を失う。その時不思議なことが起こった。病院に運び込まれていた蓮司は気が付くと大きな違和感を感じた。何と2019年の蓮司の意識は11歳の少年に戻っていたのだ。そして、2019年の蓮司の意識は1999年の4月に跳び、野球の練習試合中に頭にボールを受けて倒れた少年の中に入っていったのだ。2019年から1999年に跳んだ蓮司はこの事を知っていた。それは、20年前に自分が書き残していたノートに書かれていたからだ、そして、蓮司は宮城県から神奈川の鎌倉まで行かなければならなかった。あることを実行するために。時間は限られている。それは既に観測されて、決まったことだったが、それはこの1999年でもそうなのだろうか?
この小説は1999年と2019年が交互に描かれていて、少しづつ何が起きていたのかが明らかにされながら進んでいく。そして、本の真ん中あたりで、1999年に起こったことがだいたい語られ、2019年で蓮司の意識が過去に跳ぶところにたどり着く。そして、そこからはこの小説の登場人物は何が起きるかわからないのだ。前半は登場人物が何が起きるかわかっていて、それをなぞりながら、少しづつ進んでいく(1999年の意識を持った蓮司だけが何があったのかをよく知らない)のだが、真ん中から先は、作者だけがどうなるかわかっている領域だ。この対比的な構成が面白いし、物語もテンポよく進んでいき、誰がその犯罪の黒幕なのかも後半で明らかにされていく構成になっていて、非常に面白かった。