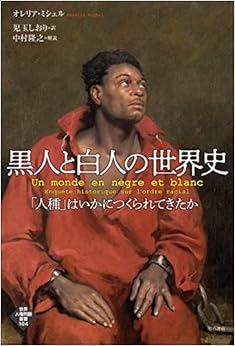オレリア・ミシェルの黒人と白人の世界史――「人種」はいかにつくられてきたか (原題 Un monde en nègre et blanc)を読んだ。
原題の意味するところは「黒と白の世界」で、日本語に翻訳すると直接的過ぎるような表現になっている。それからすると日本語のタイトルの方が穏当のような気がする。しかし、本書が扱っているのは、黒人と白人という単純なことではなく、人種というのはどこからやって来た概念なのかという事を歴史的な背景から説明している。そのために、本書の大部分は15世紀から始まる大西洋貿易時代の奴隷制に費やされている。著者は人種という概念は、奴隷制が消滅していく18世紀末から19世紀末という長い時間をかけて形作られたものだと指摘し、ヨーロッパ人はアフリカ人を奴隷にしたので人種主義という概念を生み出し、人種主義者になったというのだ。
意外だったのが、西ヨーロッパではローマ帝国崩壊後から中世末期のキリスト教の諸王国では奴隷制はほとんど消滅していたという事だ。それは当時の経済の中心地は東地中海で、南ヨーロッパでは大邸宅の召使として多くの奴隷が使われていたが、西ヨーロッパは貧しく、奴隷との交易の経済に参加できなく、人口も少なかった。フランク王国の王によって生産された奴隷は地中海のイスラム諸国に売られた。王国内の大荘園で使われていた奴隷は、次第に奴隷としての性質を失い、「隷属するもの」、「農奴」という範疇で土地に結び付けられるようになった。
ここで登場した「農奴」という言葉も、では奴隷と何が違うのかという事が以前から疑問に思っていたのだが、本書の奴隷の定義を見て、理解が深まったように思える。本書で奴隷をどのように定義しているかというと、奴隷が働く社会では、奴隷は部外者であり、社会の構成員と同じ条件で社会の再生産に参加できないと指摘している。一方自由な人は時間差の相互扶助の参加によって結びつけられている。つまり、現役の人は自分の分だけではなく、年老いた親や子供の生活のために働いている。しかし、奴隷は雇われている社会のために働くのみで、彼らには親族性はなく、奴隷は生産はするが、再生産のサイクルには貢献できないのだ。
やがて奴隷制は非難の対象になり、禁止されていくのだが、一方奴隷が担っていた労働が急になくなるわけではない。その奴隷が担っていた労働は小作制に置き換わっていくのだが、彼らは市民の権利を有していなく、単なる農民なのだ。そして、奴隷制の時のように、支配・被支配の関係性を維持するために人種という幻想が作られて行ったというのが本書の説明である。人種という概念は19世紀前半に政界、植民地社会、科学界で確立していった。人間とその身分の不平等性を科学的に正当化しようとする意味で、「科学的人種主義」と呼ばれているようだが、どう考えても非科学的だ。西洋美術とレイシズム - 隠居日録に出ていたノアの息子のハム物語も、18世紀のフランスで更新された伝説のようで、それは人種差別に基づいての聖書の解釈だ。
結局制度としての奴隷制は廃止されたが、未だに奴隷的労働というのは存在している。それは奴隷制が持っていた経済的な利益を結局は手放すことができなかったためだ。本書に1900年初頭にイギリス人がマレーシアのプランテーションに中国人労働者を連れてくるのに用いた「クレジット・チケット制」というのが紹介されている。それは労働者を集めるブローカーが労働者の将来の給与に相当する渡航費用を前払いする(労働者を雇用者に売り、労働者はその借金を抱える)制度だ。これとよく似たことが数年前から日本で起こっていて、だから諸外国から奴隷労働だと非難されているのだろう。
この本は非常に興味深い内容で、良い本だと思うのだが、―(ダッシュ)の翻訳のしかたが原文の通りのようで、日本語としてはかなり不自然に感じられ、ちょっと読みにくかった。また、全体に日本語として不自然な翻訳があり、その点も読みにくかった。非常に残念だ。