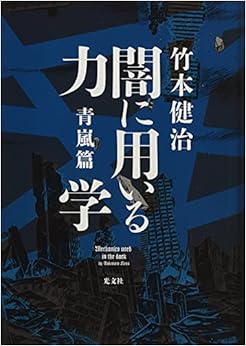竹本健治氏の闇に用いる力学 青嵐篇を読んだ。闇に用いる力学3部作の最終巻だ。読み終わた時の率直な感想は「またしても竹本マジックが炸裂か!」というものだ。青嵐篇の中でもちらりと出てくるし、初版の赤気編のあとがきにも書かれているがテーマの一つは「集団的な狂気」だ。メルド、ウバステリズム、超能力というものに好むと好まざると対峙した時、そのような事件に巻き込まれていく集団の狂気という事が、嫌と言うほど描かれている。虚構という小説の中の出来事なので、登場人物が信じようと信じまいと作者が物語として書けばそれは小説内の事実になってしまい、そのことにより登場人物は右往左往したり、それに立ち向かったりするわけだ。しかしだ、この小説にはそこに別なもの二つが投げ込まれているのだ。
一つは、「赤気編」から挿入されている「生首ファイル」と呼ばれる登場人物が遭遇した出来事を第三者の視点で淡々と描写ような文章だ。その最初の文章が物語に挿入された後に、登場人物がその内容の正しさにお墨付きを与えたことで、作者以外の何者かがどこかからこの物語を見ているという物語的次元が加えられた。しかしだ、読者にとってはこの文章は小説の文章と区別がつかない。どれが小説で、どれが「生首ファイル」なのか正確に言い当てることができない。ただ「生首ファイル」の内容が小説内事実一致するならば、特に混乱は起こさないだろうが、誰が小説内事実と一致することを保証してくれるのだろうか?
以下内容に触れている。
もう一つは物語の世界が少なくとも2つに分裂してしまったことだ。あるストリーラインでは身の危険を感じて身を隠して行方が分からなくなっていた人物が、別なストーリーラインでは他の人物と行動を共にしていたりしている。また、ある人物の過去のエピソードが祖父にまつわるものだったのが、別なところでは祖母になっていたりもしている。このようになってしまうと、何が小説内事実なのかもわからなくなってしまう。
小説的な結末はあるが、分裂した物語は収拾がつかない形で広がり続けて終わることはないのだろう。なぜなら、一つの物語の終わりは、また別な物語の始まりなのだから。